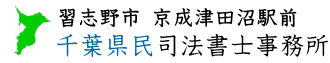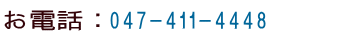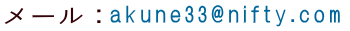- 千葉県習志野市津田沼・千葉県民司法書士事務所
- 債務整理
- 個人民事再生の詳細(その7)
個人民事再生の詳細(その7)
※個人民事再生の詳細(その6)の続きです。
「住宅資金貸付債権に関する特則」
1 経緯
バブル経済崩壊後の経済の長期低迷により,住宅ローンを抱えた個人債務者が急増している。
リストラや収入減によって,将来の昇給を見越してゆとり返済制度により返済額が増えたにも拘わらず,支払いが困難となり,サラ金等から借金をして住宅ローンの返済をするという現象が起こっています。
今までは,自宅を保持して債務を整理する方法としては,特定調停か任意整理という方法がありましたが,債権者の個別の同意を得なければならず,必ずしも,自宅を確保しながら債務の整理ができるという状況にはありませんでした。
そのため,急増する住宅ローンを抱えた債務者を救済するために,平成12年の民事再生の改正によって,この特則が制定され,平成13年4月1日から施行されることになりました。
2 目的
民事再生,破産の何れも住宅に設定された抵当権は別除権とされ,原則として,各手続に拘束されることなく担保権を実行することは可能です。
しかし,この特則では,担保不足見込み額に関係なく,住宅ローンの全額について一般再生債権とは別扱いして,住宅を保持しながら(抵当権の実行を回避でき る),他の一般再生債権を処理するということを目的としております。なお,一般サラ金等からの借入れは一切なく,債務は住宅ローンだけであるという債務者 についても,民事再生申立ての要件が整えば,利用することが可能です。
3 特色
- 債務の支払期限等の変更(199条)
- 住宅ローンの減免はない
- 住宅ローン債権者の同意は不要
- 特別条項を設けて認可されれば,保証人にも対しても効力を有する(203条1項)
- 住宅ローンの保証会社が代位弁済をした後でも,6か月以内であれば,この特則を利用でき,認可されれば,代位弁済はなかったことになって,元の住宅ローン債権者に債権が戻る(巻戻し)(198条2項,204条)
- 民事再生法には,担保権実行中止の申立て制度があり,これには厳しい要件があるところであるが,この特則を利用する場合には,住宅資金特別条項付再生計画案が認可される見込みがあるかないかだけの要件に緩和される(197条)
- 民事再生法の特則であることから,この住宅資金特別条項を設ける場合には,通常の民事再生,小規模個人再生,給与所得者等再生の何れかの申立てをしなければなりません。
4 適用要件
- 住宅(196条1号)
- 個人である再生債務者が所有していること(所有には共有も含む)
- 自己の居住の用に供する建物であって,その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの
- 投資用マンション等は除かれます
- 「供する」とされており,「供している」とはなっていないため,生活の本拠として自宅を購入したが転勤に伴って,その自宅を賃貸しており,将来自己の居住のために使用する予定があれば,要件を満たす
- 居住用の建物を2つ以上所有しているときは,主として居住している建物(1棟)のみである
- 住宅資金貸付債権の要件
- 住宅の建設,購入,改良の何れかにかかる貸付金であること
・住宅の購入には土地や借地権の取得も含み,改良とは増改築やリフォームを含みます。 - 上記借入金について,分割払いの定めがある。
- 上記貸付金またはその貸付金を保証することを業とする保証会社の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること
・土地建物の共同担保でも構わないし,その他の不動産との共同担保でも構わない(しかし,抵当権の実行手続中止命令の対象にはならない)
・根抵当権や1号仮登記も含む。
・親族等が保証人になっており,代位弁済をしても,要件を満たさない。
・抵当権は住宅に設定されていなければならず,例えば,土地には設定されているが建物に設定がされていない場合には,この特則を利用することはできない。
- 住宅の建設,購入,改良の何れかにかかる貸付金であること
- 住宅資金特別条項が定められない場合
- 住宅の上に,住宅資金貸付債権(住宅ローン)以外の債権を担保するための担保権が設定されているとき(198条1項但書前段)。
・住宅資金特別条項は,住宅資金貸付債権(住宅ローン)にのみ効力が及び,それ以外の担保権は別除権として,手続外で担保権の実行等を行うことができる結果,自宅を保持することができなくなり,特則を利用しても無意味になってしまうから
事例
土地
夫 持分10分の9
妻 同10分の1
抵当権
1番(あ)債務者 夫 抵当権者 住宅金融公庫
1番(い)債務者 妻 抵当権者 年金資金運用基金
2番 債務者 夫 抵当権者 東京海上火災保険㈱
3番 債務者 夫 抵当権者 日本信販㈱
※1番抵当権については,住宅ローンの変更契約によって,連帯債務関係が生じているが登記には反映されていない。
※なお,2・3番は住宅ローンに関する保証会社の求償権を担保する住宅資金貸付債権である。
- 住宅以外の不動産に対しても共同担保として抵当権が設定されている場合で,当該不動産に住宅資金貸付債権以外の債権を担保するために住宅ローンの後順位抵当権が付着している場合(198条1項但書後段)。
・住宅以外の不動産に対する後順位担保権者が当該不動産の抵当権を実行した場合,住宅ローン債権者は,当該不動産の売却代金から債権額に満つるまで弁済を受けることができますが,後順位担保権者は,住宅ローン債権者に代位して,住宅ローン債権者が住宅の代価から弁済を受けることができた金額まで住宅に設定された抵当権を実行することができるようになり,この結果,後順位担保権者は代位によって住宅の上の抵当権を取得し,自由に抵当権を実行することができ,自宅保持ができなくなってしまうため。
- 保証会社の代位弁済後6か月が経過した後に再生手続の開始の申立てをした場合
・保証会社が代位弁済後に再生計画の認可決定が出た場合は,当該保証債務に履行はなかったものとして(204条1項),債権が元の債権者に復帰します(巻き戻し)。
- 住宅ローンの借り換えで,住宅ローン以外に一部事業資金等を併せて抵当権を設定した場合
- 住宅の上に,住宅資金貸付債権(住宅ローン)以外の債権を担保するための担保権が設定されているとき(198条1項但書前段)。
- 住宅資金特別条項の内容
住宅資金特別条項とは?
再生債権のうちで,住宅資金貸付債権を含む場合に,住宅資金貸付債権について,(1)期限の利益回復型(199条1項)(2)最終弁済期延長型(同条2項)(3)元本据置型(同条3項)(4)同意型(同条4項)(5)原契約書通り型の何れかの型で変更することを内容とする再生計画の条項をいいます。
- 期限の利益回復型(原則)
再生計画認可決定確定時までに弁済期が到来する住宅ローンの元本部分+これに対する再生計画認可決定確定後利息+上記元本部分に対する再生計画認可決定確定時までの利息・損害金を再生計画で定める一般弁済期間内に支払えば期限の利益を喪失しなかったものと扱われ,再生計画認可確定後に到来する部分は原契約書に従って支払うとするもの
- 最終弁済期延長型(例外1)
(1)によっては,住宅ローンに返済が困難であり,再生計画が遂行できる見込みがない場合に定めることができる。
最終弁済期を延長させるものであるが,次の要件を満たさなければならない。
- 住宅ローンの元金及びこれに対する再生計画認可決定確定後の約定利息並び再生計画認可決定確定時までに生ずる住宅ローンの利息及び不履行による損害賠償の全額を支払うこと
- 約定の返済日より10年を超えず,かつ,再生債務者の年齢が満70歳を越えない範囲での延長しか認めない
- 住宅ローンの元本と利息の支払方法については,概ね従前の契約の通りでなければならない
・従前の契約が元利均等払いであれば,計画案も元利均等払いにし,元金均等であれば,元金均等でなければなりませんが,ボーナス併用返済を毎月のみにしたりすることは可能である(併用でも毎月の返済ということは変わらないし,一年の返済総額も大きく違わないため)
- 元本据置型(例外2)
(2)の方法によっても住宅ローンの返済が困難である場合,最終弁済期の延長に加えて,一般再生債権弁済期間中は,住宅ローンの元本の一部及び住宅ローンの元本に対する利息のみを支払うというもので,かつ,上記(2)①②③の要件を満たさなければならない。
- 同意型
住宅ローン債権者の同意により,いかなる計画案の策定も可能
- 原契約書とおり(そのまま型)
個人再生の開始決定がでると,弁済禁止効(85条)により,再生計画認可確定まで弁済を行うことができず,これまで住宅ローンを遅滞無く支払ってきたとしても,期限の利益を喪失し遅延損害金等がついてくるのが通常でした。
これを回避するために,第三者弁済や保証人からの弁済を行ってきたこともありましたが,平成14年の法改正により,許可弁済の制度ができました(197条3項)。
- 期限の利益回復型(原則)
要件
- 再生債務者が,再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付債権の定めにより(期限の利益喪失約款),当該住宅資金貸付債権の全部または一部について期限の利益を喪失することとなる場合であること
- 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあること
を条件に裁判所に対して許可を求めるというものです。
(注:約款によれば,再生手続の申立てをしただけで期限の利益を当然に喪失するという条項があるが,しかし,実際は,再生債務者が分割弁済をしていれば期限の利益を喪失していなかったものとして扱われているため,この一事をもって要件を満たしていないとはいえない)
抵当権の競売手続の中止命令(31条・197条)
1 通常の民事再生における競売手続の中止命令(31条)
要件
- 再生手続開始の申立てがあった
- 再生債権者の一般の利益に適合する
- 競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがない
※「一般の利益に適合する」とは,再生債務者が誠実に手続を進行させており,再生する可能性が高く,再生には,当該競売物件が不可欠または有益であり,競売を進行させてしまっては,再生が不可能もしくは困難になる場合,または,再生にとって不可欠ではなくても,換価の時期または方法によっては高額に処分が 可能であって,再生債権の弁済率を上昇させることが認められる場合。
「不当な損害を及ぼすおそれがないとき」とは,仮に損害があったとしてもそれが受忍すべき限度内であることをいい,具体的には①目的物の価格が被担保債権 額を超えている②生産設備・在庫商品のように利用や売却によって急激に価値が下がってしまうような場合,目的物に代る他の物を提供したり,価値の低下に見合う弁済をしたり,弁済をする見込みがあるときなど(個人住宅の場合には,ほとんど考えられない手続である。)
2 抵当権競売の中止命令(197条)(資料14)
要件
- 再生手続開始の申立てがあった場合
- 住宅資金特別条項を設けた再生計画案の認可の見込みがある場合
3 「抵当権の実行としての競売」(住宅ローン以外)
共益債権(法119条)や一般優先債権(租税債権等法122条1項)の場合は,再生手続によることなく随時弁済を受けることができる。これらの支払いをしない場合は,訴訟を提起され,また,強制執行をされてしまう。
この競売手続きを中止させるには,法121条3項,122条4項によって中止または取消しを求める必要があるが,要件が,①強制執行が再生に著しい支障を及ぼさない,②再生債務者が他に換価容易な財産を十分に有している。
現実的には,個人の場合,不可能。
この場合,結局は,自宅を失うことになり,住宅資金特別条項が定められず,再生計画不認可決定を受けることになる。 その後,住宅資金特別条項を設けない個人再生の手続を再度なすか,破産をせざるを得ない。
事前協議
1 再生債務者は,住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合は,予め住宅ローン債権者と協議しなければならない(規則101条1項)。
住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出しようとする場合は,再生計画案の立案段階までに住宅ローン債権者に対して,自己の収入・家族状況・一般再生債権の弁済額等の情報を開示して,具体的に履行可能性の高い計画案の立案を住宅ローン債権者の助言を受けながら行う必要があります。
事前協議に必要な書類として
- 源泉徴収票
- 3か月分の給与明細書(同居者がいれば同居者のものも)
- 住民票
- 返済計画表
- 当該住宅等の登記簿謄本
- 家計表
住宅資金特別条項を設けた再生計画案の不認可事由(202条2項)
- 174条2項1号または4号に規定する事由があるとき(202条2項1号)
- 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき(同項2号)
- 再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき(同項3号)
- 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき(同項4号)
千葉県習志野市・京成津田沼駅すぐ 千葉県民司法書士事務所
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談をお寄せください。
迅速に回答をさせていただきます。
お電話:047-411-4448(月~金 9時30分から19時)
メール:akune33@nifty.com(メールは24時間受付)